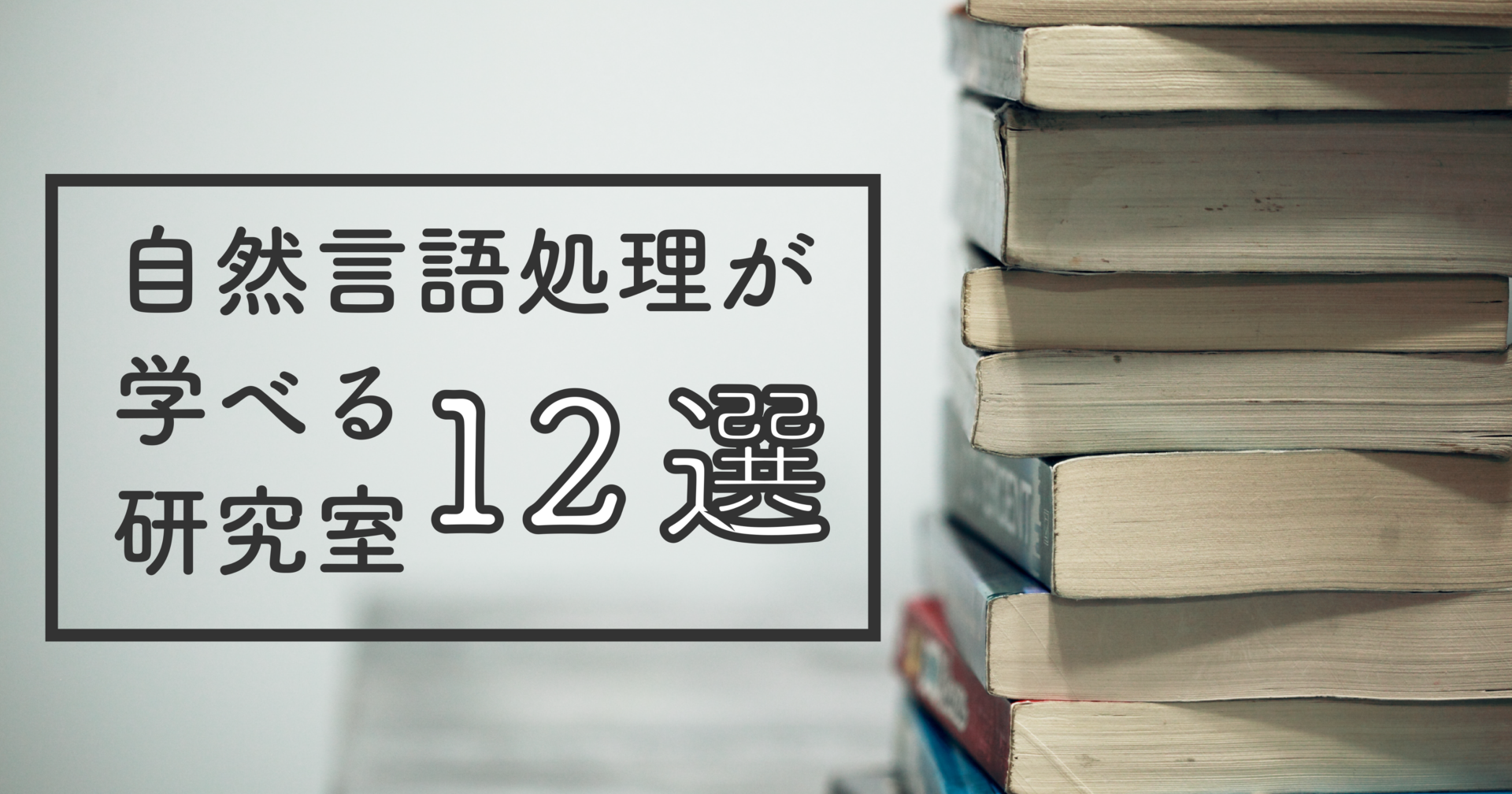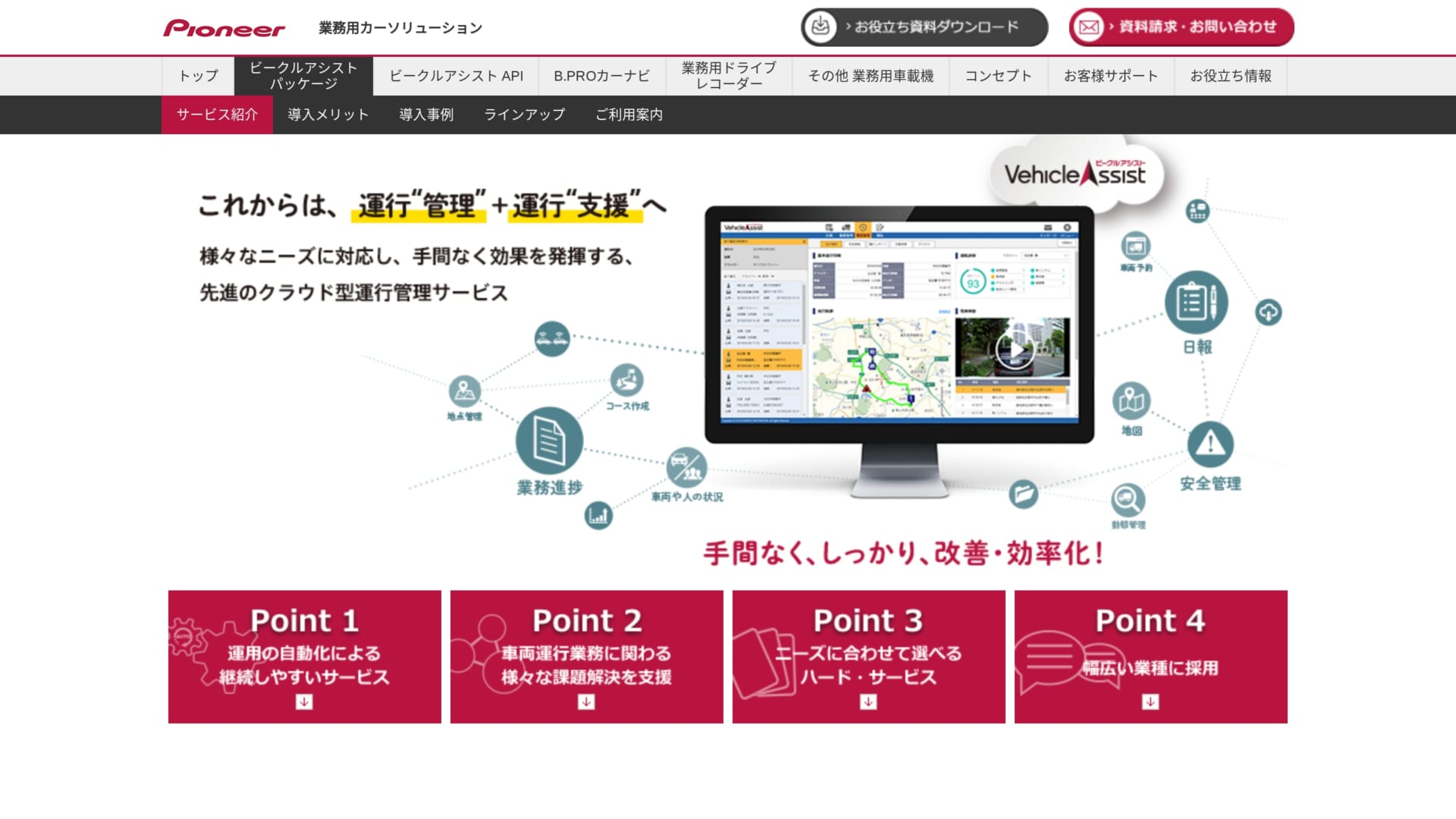AINOW編集部作成
エッジAIが近年注目されています。富士経済グループの予測によると、エッジAIは2018年度に見込み110億円だった市場規模が2030年度には664億円にまで拡大するそうです。
(※参考:本格的な導入が進む国内のAI(人工知能)ビジネス市場を調査 – 富士経済グループ)
従来のAIのようにクラウド環境で情報の処理を行う必要がないエッジAIはデバイスのみで迅速な処理ができ、特に即時対応が求められる領域で活用が広がっていくでしょう。
そのため、IoTと非常に相性が良く、IoT技術の成長・拡大に伴って、エッジAIの開発の重要性も増していくと予想されます。
目次
エッジAIとは
エッジAIとはその名の通り、エッジ(端)に搭載されているAIのことです。ここでいうエッジとはカメラや車、工場の機械デバイスのことで、そのようなエッジの端末に直接AIを搭載し、情報処理をする技術です。
ここでは「エッジAIとクラウドAIとの違い」「エッジAIの種類」「エッジAIのメリット」を紹介します。
エッジAIとクラウドAIとの違い
エッジAIに対して、クラウドAIとは大量のデータをネットワークを通してデータセンターなどに送信し、データセンター内のハードウェア(CPUやGPU)を利用して高速学習するものです。
GAFAのサービスなどをはじめ一般的なAIの多くがクラウド型AIとして提供されています。以下が両者の大まかな違いです。

AINOW編集部作成
2つのタイプに分かれるエッジAI
クラウドAIとエッジAIの違いについて解説しましたが、実はエッジAIにも2つのタイプがあります。
- エッジAI上で推論(判断)のみ行い、クラウドとの接続で学習データやモデルの更新をするタイプ
- エッジAI上で推論と学習を行い、クラウドとの接続を必要としない完全独立型のタイプ
の2つです。
ディープラーニングなどの機械学習技術は、膨大なデータ処理を必要とするため、エッジデバイスで学習を行うと、長時間に渡って学習を行う必要があります。
そこで、リアルタイム性を要する推論(判断)部分だけをエッジデバイス側で行い、学習はクラウド上で行う形が一般的になっています。
エッジAIとIoTの関連性
SoftbankWorld 2018(2018年)で、ソフトバンクグループ代表取締役会長兼社長の孫正義氏は、「2035年までには1兆個を超えるIoTデバイスが私たちの身の回りに溢れる」と話しています。
DC Japanによると2018年時点でも、日本のIoTの市場規模は6兆円にまで成長しており、これから、さらにIoTデバイスの普及が進んでいくと予想されます。
IoT:Internet of Thingsの略。さまざまな「デバイス」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する仕組み。近年では、スマートスピーカーやスマートフォンと連携したスマート家電なども普及が進んでいる
また近年、エッジAIが世界的に注目・開発されるようになった理由はIoTの成長によるものだけに限りません。エッジAIの研究開発を行う「AISing」の代表取締役CEOの出澤純一氏によると、
自動運転車や、第4次産業革命に伴う工場の自動化の推進が世界で注目を集めており、その実現にエッジAIが不可欠であること
技術の進化によってこれまでエッジAIの導入には不十分であった計算環境が整ってきたことで、具体的な実装化が進んでいることがエッジAIが注目される要因となっているそうです。
エッジAIのプロセッサー
プロセッサーとは、簡単に言うと「AIが処理を行うための脳となる部品」です。
エッジAIではその端末に、クラウドAIではサーバーに搭載されており、さまざまな種類があります。
性能と電力で比較した図が左側。左の図を元にコストパフォーマンス(性能と消費電力との比率)と汎用性で比較した図が右側の図です。これは新製品の登場で関係性が変わることもあるので一例としてみてください。

AINOW編集部作成
エッジで利用される計算プロセッサは、低消費電力が重宝されます。
そのため、上記の図からでは「消費電力が少なく、ASICのコストパフォーマンスが良いからASICを使えばいいのでは?」と考えてしまいがちですが、近年のアルゴリズムの複雑さ・高速化の進化にASICが追いついていない場合もあり、一概にコストパフォーマンスだけではプロダクトの良し悪しを測ることはできません。
GPU型
IoTに向いており、汎用性があるのがGPU型です。
SoC(システムオンチップ)により、低消費電力・小型化が図られているプロダクトも散見されます。例としてNVIDIAのTegraなどです。しかしそれでも消費電力は大きいのが難点です。
ASIC型
特定の用途に関してはASIC型に軍配が上がります。
特定のアルゴリズムを一定期間使用する場合、ASICの電力効率は群を抜いて良いです。ただ特化している分、昨今のアルゴリズムの変化に対応しきれていない場合もあります。
FPGA型
FPGA型は日々成長しているアルゴリズムをすぐに実装・展開可能な柔軟性が特長です。ただ基本的には低速で電力消費が高いため性能を重視する場合には要検討です。
エッジAIの鍵となるプロセッサー分野には多種多様のプロダクトがあるため、丁寧に比較検討して自分のニーズに一番合う計算プロセッサーを見極める必要があります。
エッジAIを活用するメリット
リアルタイムでの処理
端末上に搭載されているエッジAIは、その場でのリアルタイムの処理やインターネットが繋がらない環境での処理を可能にしています。
通信コストの節約
端末で集積したデータをクラウドに送る際には、データの選別によってコストを抑えることができます。
AI開発には多額のコストがかかってしまいますが、エッジAIはさまざまなデバイスでの利用が可能であることや開発環境の発展によって低コストで開発することができます。
セキュリティ強化
プライバシーの問題が常につきまとうデータ管理に対しても、クラウド上にデータを送らずに端末内での処理に留めてくれるエッジAIは安心であり、情報保護の観点からも優れているといえます。
エッジAIを活用するデメリット
大規模な処理が困難
端末上で処理を行う形式であるエッジAIは、クラウドAIに比べて小規模なリソースであるためクラウドAIのように大規模な処理を行うことを苦手としています。
システムの複雑化
クラウドAIに利用されるエッジ(端末)はデータの収集とクラウドへの転送が主ですが、端末で完結できるエッジAIで利用される端末は複雑なシステムを持つことになります。
エッジAIの活用事例
ここではいくつかエッジAIの事例を紹介します。一般的に、エッジAIが実際に利用されている・利用されうる場面として
- 自動運転
- 公共の場所での物体認証
- 気象予報
- 自律ドローン
- 工場での検品
- 小売店などのトラフィックデータ回収
などがよく挙げられます。その中でもここでは工場での実装例・小売店でのトラフィックデータの実験例・公共の場所での物体認証実験例を紹介します。
オムロンとのエッジAI共同開発
エッジAIの活用例として、株式会社エイシングとオムロン株式会社(以下オムロン)が共同開発した巻き線機にエッジAIがあります。巻き線機とは巻き線からコイルを製造する機械で以下の図のような機器です。

提供:株式会社エイシング
従来であれば、不具合が発生すると、20mほどの不良品が発生していましたが、制御周期 (125 μ秒) 毎に、数十ミリ秒先の影響を予測する 制御+超現場型AI技術により不良品廃棄が3分の1以下に低下しました。
エッジAIカメラで来店客のプライバシー領域を自動マスキング
株式会社ヘッドウォータースと株式会社セキュアが行った「comieru Live」というソリューションの実証実験があります。
来店した客をマスキングすることでプライバシーを守りつつ、飲食店などの空席情報をリアルタイムにWeb上へ掲出できる混雑状況が見えるというものです。
エッジAIにより電車に挟まる物体検出・伝達を0.3秒程度で可能に
川崎重工業の車両カンパニーが行なっているプロジェクトが駅での「戸挟み検知」です。車掌が目視確認をした判断する現状に対して、川崎重工は設置されたエッジAIが物体検知をした際、車掌に知らせるシステムを作りました。
実運用に耐えるためには異常検知から車掌に伝達するまでの間をわずか2秒以内にする必要があったためネットワークを介した一般的なAIではなく、エッジAIを利用したそうです。
エッジAIを利用したモデルの実証実験では、たった0.3秒程度で異常検知→情報伝達が可能という結果になり、今後さらに研究を進めれば、本番運用できる状態にまで持っていける可能性が十分高いです。
エッジAIが医療界を支え、患者の治療効果改善へ
Intelは医療現場におけるエッジAIの導入に力を入れており、タブレットやウェアラブル端末、ヘルスモニターといったさまざまなデバイスでの利用を可能にしています。
これによって医師の業務効率の向上や患者のケアのクオリティアップに成功していますが、これに加えてデータの生成もエッジAIは医療現場にもたらしています。
患者のモバイルデバイスや病院の機器でデータを集積することが可能となっています。
各社のエッジAI開発・導入状況
次に有名企業のエッジAIにまつわる現状について紹介します。ここではエッジAIを専門とする企業だけでなく、GAFAMのような巨大IT企業の例も取り上げています。
海外企業
ここでは海外企業のうちGAFAMの動向を含めて紹介します。
GoogleはASICタイプのエッジAIであるTPUを搭載した「Coral Dev Board」などを販売しています。
Apple
AppleもエッジAIに力を入れており、「Spectral Edge」という企業を昨年買収していることからもその傾向は強まっていると言えるでしょう。iPhone X 以降に搭載されている「Neural Engine」などは有名です。
Facebookは2019年3月には、ハードウェアプラットフォームである「Zion」やの推論用の回路である「Kings Canyon」やASICタイプの「Mount Shasta」などを開発・発表してエッジAI業界に参入しました。
AWS
AWSからは「AWS IoT Greengrass」のようなエッジデバイス機器の他にも「Amazon SageMaker Neo」といったエッジAIのプラットフォームの最適化を行うサービスも提供されています。
Microsoft Azure
マイクロソフトは「Azure」の知見を生かしたサービス「Azure IoT Edge」や
エッジAIのプラットフォームを構築できる「Azure Sphere」など複数のサービスを提供しています。
NVIDIA
GPUのリーディングカンパニーであるNVIDIAは「Jetson Nano」と言ったプロセッサー以外にも、エッジAIカメラ「MRM-900」なども提供しています。
Intel
“Intel”はFPGAを主力製品とする米企業”Altera”をFPGA部門に組み込み、FPGA型に力を入れてサービスを提供しています。
IBM
IBMでも5Gも視野に入れている「IBM Edge Computing」というプラットフォームを提供しています。
Arm
イギリス企業である「Arm」は「Arm Cortex」というCPUを提供している他にも「Arm Mchine Learning Processor」といったプラットフォームのようなサービスも提供しています。
AMD
コンピュータプロセッサーの分野などで勢いのあるAMDはエッジAIの基礎とも言えるGPUやCPUを各メーカーに提供しています。
国内企業
海外企業はスケールが大きく、有力で優秀なプロダクトも多く開発されていますが、国内企業も負けていません。例として、日本のLeapMind社は米調査サービスのCB insights社が出した「AI 100 2018」にも選出されており、世界的にも評価されています。
LeapMind
組み込み型ディープラーニングを共同研究しているLeapMindは昨年2019年にディープラーニングの推論処理に特化した低消費電力プロセッサIP(Intellectual Property)の開発を昨年明かしており、エッジAIへの参入を本格化しています。
AIsing
AIsingエッジプロセッサーが学習と推論の両方を行う、エッジデバイス組み込み型のAIアルゴリズム「ディープ・バイナリー・ツリー(DBT)」をはじめとしたエッジAI中心のプロダクトを提供しています。
EDGEMATRIX株式会社
2019年に米国Cloudian Holdings Inc.からスピンオフしたEDGEMATRIXは(エッジAIの導入をトータルサポートする「Edge AI Solution」などのサービスを提供しています。
Idein
Ideinは画像認識や音声認識をメインとした、エッジコンピューティングプラットフォーム「Actcast」を提供しています。
エクスウェア
エクスウェアは組み込みAIソリューションを提供しており、様々なAI技術をRaspberry Pi (ラズベリーパイ) 等の基盤上で動作させる仕組みとなっています。
OKI
電子通信機器として有名なOKIは「AE2100」というエッジコンピューターを提供しています。
富士通エレクトロニクス
同企業から提供されている「組込みAIソリューション」では、デバイスやプラットフォームの提供に留まらず、トータルサポートを行います。
ここでは多く存在する企業のうち、一部を取り上げました。エッジAI専門の企業はNVIDIAのようなグローバル企業だけでなく、多くの日系企業もエッジAIを開発しているのがわかりますね。
エッジAIの今後
現場で完結する、リアルタイムでの処理を行うことができる、さらにはさまざまなデバイスで利用ができるなど、汎用性の高いエッジAIは今後更に広範囲に渡って応用される分野でしょう。
医療や建築、地域行政などどのような分野でも応用を利かせることが可能なエッジAIが今後どのように発展を遂げていくか、注視して追っていく必要があります。
最後に
現在、エッジAIは非常に注目されている技術です。この記事ではエッジAIに関する初歩的な知識が得られるようにしています。
様々なAI関連技術のうち、日系企業がクラウド型AIでGAFAMなどに追いつくことは厳しいと言われています。一方、エッジAIには組み込み技術が必要であり、日本の技術力が活かせる部分であることからエッジAI関連では日本も十分世界に通用する可能性があります。長い歴史の中で日本のお家芸としてきた組み込み技術がエッジAIに十分に生かされることで今後、世界にも通用するプロダクトが多く生まれて来るかもしれません。
これから到来すると言われているIoTのカンブリア爆発が起こるためになくてはならないエッジAIの今後の発展に目が離せませんね。
初めまして。大学3年のさとしです。
大学では経済を専攻してますが、、
今はAIと統計学を中心に勉強しています。
皆さんにわかりやすい記事を発信していきます。