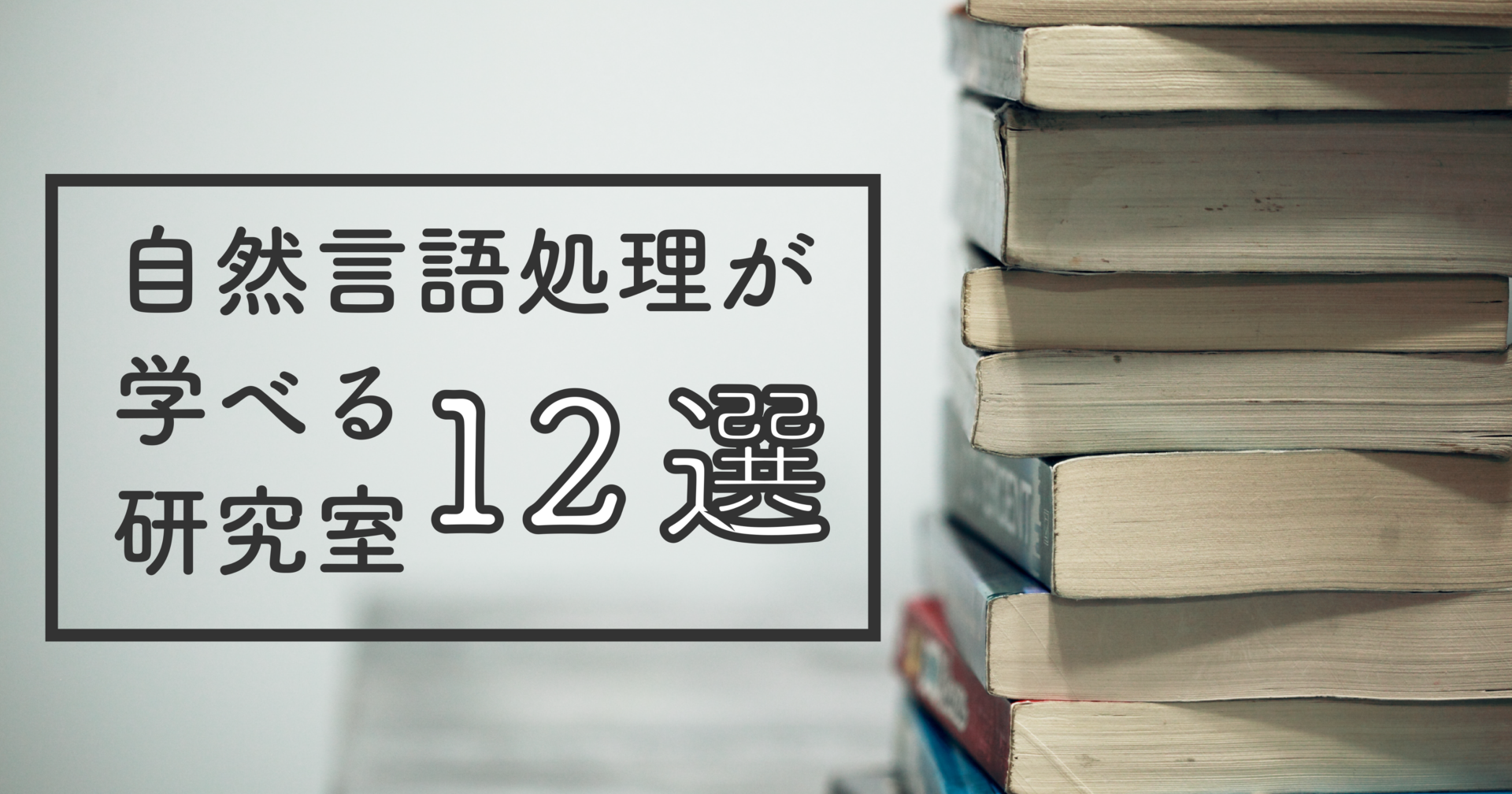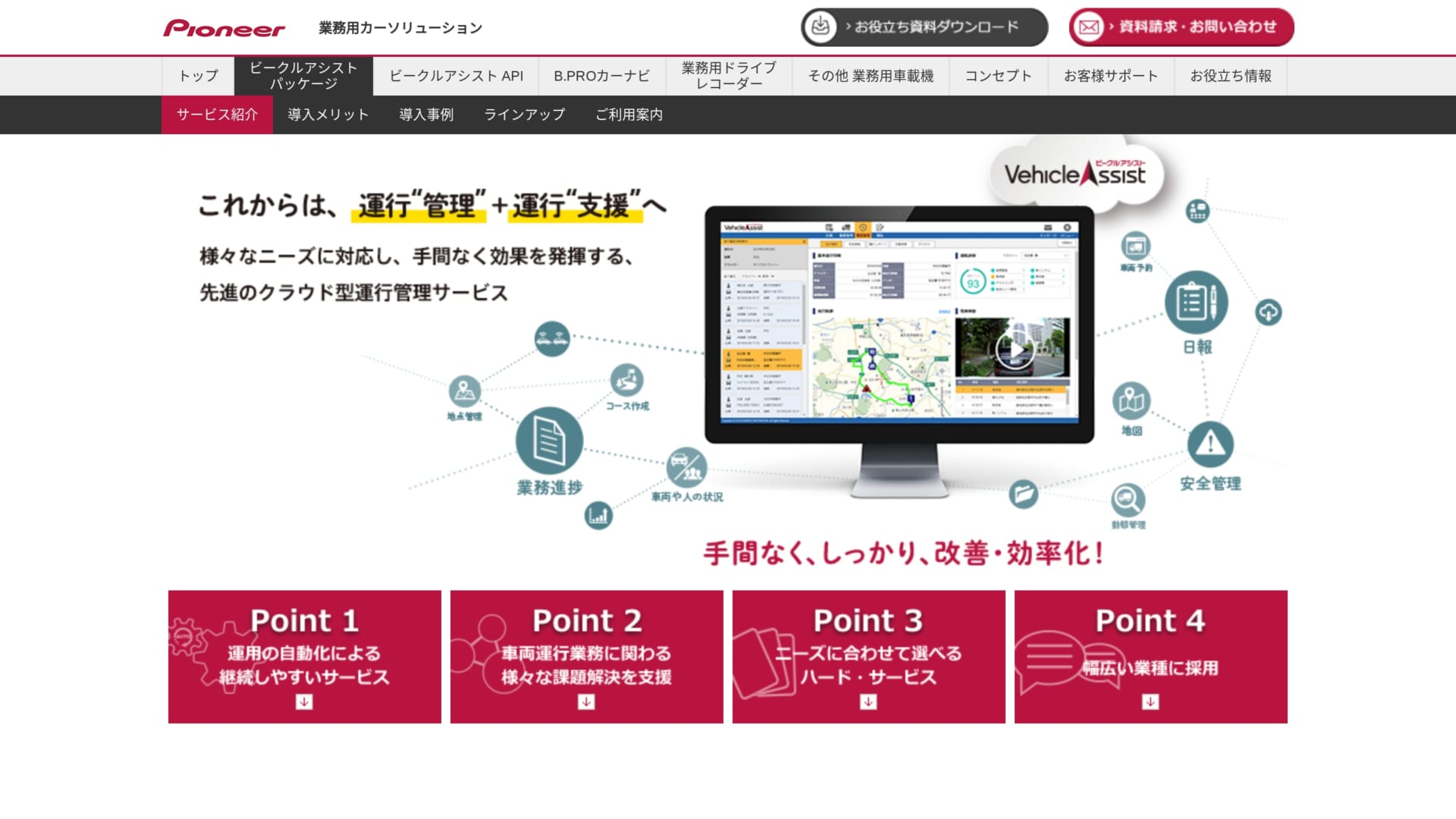AI技術が発展し、画像認識や音声認識、テキストの分析などが可能になり、技術的なブレークスルーが起きました。同時に、AIが人類の知能を超えてしまうシンギュラリティ(技術的特異点)に注目が集まっています。
AI技術が、さらに進化を遂げた未来では、AIが人類の知能を超え、指数関数的に進化し、その進化の速度が予測できなくなると言われています。そのAIが人類を超えるポイントが「シンギュラリティ(技術的特異点)」です。
今回は、シンギュラリティが具体的にどんな理論なのかを紹介し、私たちにどんな影響を与えるのか考察していきます。
目次
シンギュラリティとは
シンギュラリティの概要
シンギュラリティは、「AIが人間の知能を超える転換点」のことを指し、日本語では「技術的特異点」と訳されます。アメリカの未来学者レイ・カーツワイル氏が2005年に提唱したことで広く知られるようになりました。
シンギュラリティの到来は、「仕事を奪われる」「AIに支配される」というマイナスイメージが定着しつつあることから、近年大きな注目を集めています。
2045年問題とは?
レイ・カーツワイル氏は、シンギュラリティが2045年に到来すると予言しました。その影響から、シンギュラリティに関わる議論や起こる問題は、「2045年問題」と呼ばれています。
▼2045年問題を詳しく知りたい方はこちら
シンギュラリティを考える上で重要な「収穫加速の法則」
収穫加速の法則とは、「一つの重要な発明は他の発明と結び付き、次の重要な発明の登場までの期間を短縮し、イノベーションの速度を加速することにより、科学技術は指数関数的に進歩する」という法則です。

レイ・カーツワイル氏は、この収穫加速の法則に基づいてシンギュラリティが2045年に起こると予測しています。
収穫加速の法則の考えは、「ムーアの法則」が由来です。
ムーアの法則とは、「半導体の集積率は18か月で2倍になる(半導体の性能が18ヶ月で2倍になると同時に、コスト面も半分になる)」という理論です。
例えば、ある面積あたりのトランジスタ数が、100個とした時に、18か月後(1.5年後)には、2倍の200個、3年後には、4倍の400個、わずか7.5年後には3200個になります。
1965年にムーアの法則が唱えられてから40年間、半導体は実際にそのような成長を遂げています。
レイ・カーツワイル氏は、半導体が指数関数的に進化したことと同様のことがAIにも起こると考え、収穫加速の法則を提唱しました。
シンギュラリティに対する識者の意見
シンギュラリティを提唱したレイ・カーツワイル
2005年、レイ・カーツワイル氏は著作『The Singularity Is Near:When Humans Transcend Biology』で、「シンギュラリティは近い」と明言しました。
一般的にシンギュラリティは、「AIが人間の知能を超える時点」という意味で知られています。しかし、レイ・カーツワイル氏はシンギュラリティを、AIの能力が人間の能力を超える時点としては定義しておらず、$1,000(約10万円)で手に入るコンピュータの性能が全人類の脳の計算性能の総和を上回る時点として定義しているのみです。
また彼は、シンギュラリティが起こった場合、AIがAIを作れるようになり、その頃にはコンピュータが支える強力な知能により、人類の在り方が根底から覆っているであろうとまで予測しています。
シンギュラリティが起こると主張する人物
孫正義
ソフトバンク創業者の孫正義氏はSoftBank World 2018基調講演で、シンギュラリティの到来について以下のように主張しました。
シンギュラリティはもう一つのビッグバンです。一言で言うと、人工知能の叡智が人間の叡智を超えます。人工知能=超知性が生まれることで、さらゆる産業が再定義されるようになります。まさにシンギュラリティは人類史上最大の革命です。
▼関連記事
スティーヴン・ホーキング
イギリスの宇宙物理学者スティーヴン・ホーキング氏も、シンギュラリティの到来を主張した人物の一人です。2017年に開催された「G-Summit Tokyo 2017」にて、彼は以下のように語っています。
文明によって得られるものはすべて人間の知能の産物ですが、「生物学的な脳によって達成できること」「コンピューターによって達成できること」との間には大きな違いはないと私は考えています。
したがって理論上コンピューターは人間の知能を模倣し、凌駕できるということになります。
イーロン・マスク
テスラ社やSpace X社の共同設立者・CEOとして知られるイーロンマスク氏は、シンギュラリティについて強い危機感を抱く人物で、「AIは核兵器よりも危険かもしれない」とツイートしています。
Worth reading Superintelligence by Bostrom. We need to be super careful with AI. Potentially more dangerous than nukes.
— Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2014
また彼は、2019年に上海で開催された「World Artificial Intelligence Conference」にて以下のように語りました。
AIによって、仕事はやや無意味なものになるだろう。おそらく、最後に残る仕事はAIソフトウェアの開発で、いずれはAIが自らのソフトウェアを開発するようになるだろう。
シンギュラリティが起こらないと主張する人物
三宅陽一郎
哲学やゲームAIの専門家である三宅陽一郎氏は、AINOWの取材で以下のような理由により、シンギュラリティの理論は崩れていると主張しています。
今われわれは自分の目で世界を認識しているから、たかだか100メートルぐらいしかわからないけれど、将来的には地球全体をいつでも見れるようになるかもしれません。シンギュラリティの意味は、人の拡張によって薄れていきます。
そうすると、人工知能の見え方も変わってくると思います。生身の人間と人工知能を比較したら、やはり脅威でしかありません。でも人間はヒューマンオーグメンテーションによって進化すると考えれば、テクノロジーが宿るのは人工知能側だけでなく、身体側(人間側)にもくるということですね。
▼参考記事
新井紀子
数学者の新井紀子氏もAIが人間を超えることには懐疑的です。
「真の意味でのAI」が人間と同等の知能を得るためには、私たちの脳が、意識無意識を問わず認識していることをすべて計算可能な数式に置き換えることができる、ということを意味します。しかし、今のところ、数字で数式に置き換えることができるのは、論理的に言えること、統計的に言えること、確率的に言えることの3つだけです。
出典:新井紀子.『AIvs教科書が読めないこどもたち』東洋経済新報社.2018.p164
シンギュラリティが起こるとどうなるのか
限界費用ゼロ社会の到来
シンギュラリティが到来すると、限界費用ゼロ社会が実現するかもしれません。
限界費用ゼロ社会とは、文字通り限界費用がゼロの社会のことを指すのですが、そもそも限界費用とは何なのでしょうか。
限界費用とは、「生産1単位あたりにかかる費用のこと」です。ここからは、パン屋を例にして詳しく限界費用を説明します。
例えば、パン屋を開くのに賃料が100万円かかるとします。また、パンを1つを作る材料費が50円かかるとしましょう。
お店を開いて、パンを2個作った場合の総費用は、
「賃料100万円+(材料費50円×2)=100万100円」です。
この後、パンを10個作ろうが100個作ろうが、賃料は固定費用なので変わりません。変わるのは材料費だけです。
では、ここでもう1つパンを作るとしましょう。プラスで50円かかりますよね。
その50円が限界費用です。
「50円=生産1単位あたりにかかる費用」だからです。
限界費用がどんなものか分かったでしょうか?
多くの場合、これに人件費、運送費、売り手の利益などの費用が上乗せされます。その結果、本来50円のパンが100円で売られるということになるのです。
ところが、シンギュラリティが起こり、以下の条件が揃ったらどうなるでしょう。
|
この場合、人間が何もしなくてもパンの材料の小麦粉が手に入るため、パン屋の限界費用がゼロになることはもちろん、運送費や人件費、売り手の利益などの費用もゼロになります。
かかるのは、家賃や光熱費などの固定費のみです。
つまりシンギュラリティが起こった場合、パンは限りなくゼロに近い価格で販売されるかもしれません。
また、今回例に出したパン以外にも、野菜や洋服、食器などさまざまな物の限界費用がゼロになり得るため、それらの商品も無料に近い価格で提供される可能性があります。
ストレスが少ない社会の到来
またシンギュラリティが起こると、人々の悩みや不安が減り、ストレスの溜まりにくい社会が到来するかもしれません。
例えば、掃除を全て行ってくれる全自動片付けロボットができれば、家事の手間が省けますし、高精度の自動運転が普及すれば、渋滞にハマることなくスムーズに目的地まで行けるようになります。
家事や渋滞は人々のストレスになり得ることですが、シンギュラリティの到来によって、これらの問題は解決されるでしょう。
また、先ほど述べたように様々なものが無料に近い価格で提供されることで、ほとんど働かなくても食べ物に困らない生活が送れるようになる可能性があります。
そうなった場合、人々の貧富格差が無くなったり、エンタメを楽しむ時間が増えたりするため、人々は将来に不安を抱きにくくなり、楽でストレスのない生活を送れるようになるかもしれません。
科学技術の無限発展
どんなことでもこなせる汎用人工知能ができれば、AIが自ら仮説を設定し、それを検証するというプロセスを高速で回せることになります。
つまり、全て汎用人工知能に任せてしまえば、人間が手を加えずともAIが勝手に科学を発展させてくれるということです。
もはやAIの計算能力が早すぎるあまり、あっという間に科学技術が発展してしまうという仮説が立てられています。
引用:AIは人間最後の発明になる? 「シンギュラリティ」が現実になる日は来るのか?
シンギュラリティは本当に起こるのか
シンギュラリティが起こる可能性
シンギュラリティは本当に起こるのでしょうか。まずはシンギュラリティが起きる可能性を考えてみましょう。
進化の速度は無限大
前述の通り、収穫獲得の法則でAIは指数関数的に進化するという仮説があります。
AIの進化が指数関数的に進むと仮定すると、ある点でその進化の速度は無限大に達します。その場合、少なくとも2045年にはAIが人類の知能を上回り、もはや人間が予測できない域に達する可能性も十分にあるでしょう。
すでに一部の分野でシンギュリティは起こっている
一般的にシンギュラリティは、「AIが人間の知能を超える転換点」のことを指します。
シンギュラリティは2045年に起こると予測されていますが、すでに一部分でAIは人間の知能を超えているとも言えるでしょう。
例えば、囲碁や将棋などのボードゲームでは、AIがトップクラスのプロ棋士に勝利しました。また、医療分野のガンなどの画像診断では、AIが医師の精度を上回った事例もあります。
しかし、これらのAIは全て決まった作業をするためのAI(特化型AI)で、人間そのものを超えているわけではありません。
もし今後、なんでもこなせる汎用人工知能が登場すれば、シンギュラリティ到来の可能性はさらに高まるでしょう。
シンギュラリティが起こらない可能性
ここまでシンギュラリティが起こる可能性に着目してきました。ここからは、シンギュラリティが起こらない可能性も考察してみましょう。
性能の限界
そもそも、汎用的で万能なAIの原理がわかっていません。
人間の知能は部分的に見るとディープラーニングなどのAI技術と比べて劣っています。しかし、人間はあらゆる事象に臨機応変に対応することが可能です。
一方で、人工知能のように、1つの知能で何もかも、全てを圧倒的なレベルでこなすには、大量の記憶容量や膨大な計算パワーが必要になります。
あらゆることに柔軟な知能を実現するためには、逆にひとつひとつの性能を下げるしかないという考えもあります。このような性能の限界があるため、人工知能が無限に進化していくのは考えづらくなっています。
メタファーの力があまりにも弱い
人間は、経験が少なくても過去の経験から未知のことを想像して行動することが可能です。物事を抽象的に捉えて行動するメタファー(比喩・たとえ)の能力が人間にはあります。
今、進化が進んでいるAIは大量の経験(データ)を基にして、帰納的に物事を判断しています。そのため、AIは少ない経験(データ)から物事を想像する能力がありません。
人間は1を知って10を知ることができますが、AIは100のデータから1つのことを抽出します。つまり、人とAIは知能の方向が逆というわけです。
コラム:なぜAIのメタファーの力は弱いのか
AIには身体がありません。人間は身体(感覚器官)を通して常に現実世界を認識し、無意識でも常に予測と判断を繰り返しています。
しかし、AIには身体がないため、自分の体の規模感がわからず現実世界を主体的に捉えることが難しくなってしまいます。そうするとメタファーの力を発揮することができません。
生物固有のあり方を押し通すからこそ、万能な知能が生まれると捉えることができます。AIは世界を構成できず、メタファーの力を使うことができないのです。
そのため、人間は人工知能の身体を持たない認識の世界を確定できないのです。AIの世界をうまく把握できなくなってしまいます。
シンギュラリティが起こったとき、私たちはどうすれば良いのか
シンギュラリティは、人類に大きな影響を与えると予測されています。そのため、シンギュラリティが起こった場合、私たちはどうすればいいか分からず不安になるかもしれません。
しかし、人間は適応能力に長けています。たとえシンギュラリティで世の中が大きく変化しても、人間がその変化に対応できる可能性は十分あります。
つまり、「何もしなくていい」ということです。
例えば、10年前には誰もスマートフォンなど持っていませんでしたが、今や国民の8割がスマートフォンを所持し、それを当たり前のように使いこなしています。
また、新型コロナウイルスの影響で一気に在宅勤務や、オンライン授業が始まりましたが、比較的早い段階でリモート生活に慣れた方も多いはずです。
このように、人間は意識して努力しなくても自然と状況に適応していくことができます。シンギュラリティの到来もこれらと同様、変化に自然と適応して、何もかもAIに頼るのが当たり前の時代が来るかもしれません。
まとめ
今回は、「シンギュラリティ」について解説しました。
シンギュラリティの到来は、「仕事を奪われる」「AIに支配される」というマイナスイメージが定着しつつあります。しかし、シンギュラリティの到来で人間の生活が豊かになる可能性が高いのも事実です。
今後、私たちがもっとAIに関心を向け、AIの知識をキャッチアップしていけば、シンギュラリティが起こったとき、よりスムーズに変化に適応できるかもしれません。
また、偏った報道や議論内容を鵜呑みにすることなく、AIのポテンシャルと、その限界に関する情報を認識し続けることが大切です。
▼AIの今後について詳しく知りたい方はこちら
◇AINOWインターン生
◇Twitterでも発信しています。
◇AINOWでインターンをしながら、自分のブログも書いてライティングの勉強をしています。