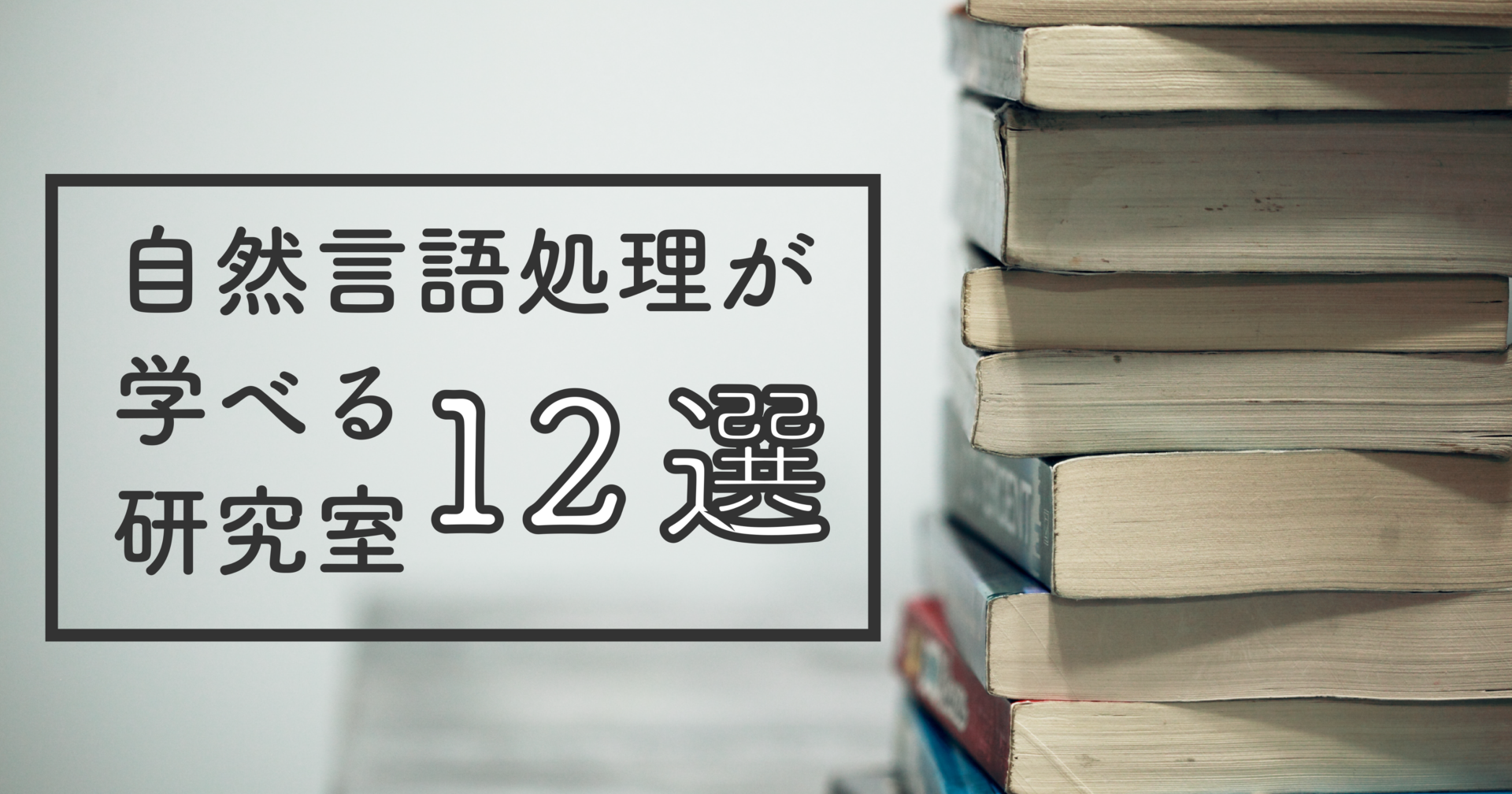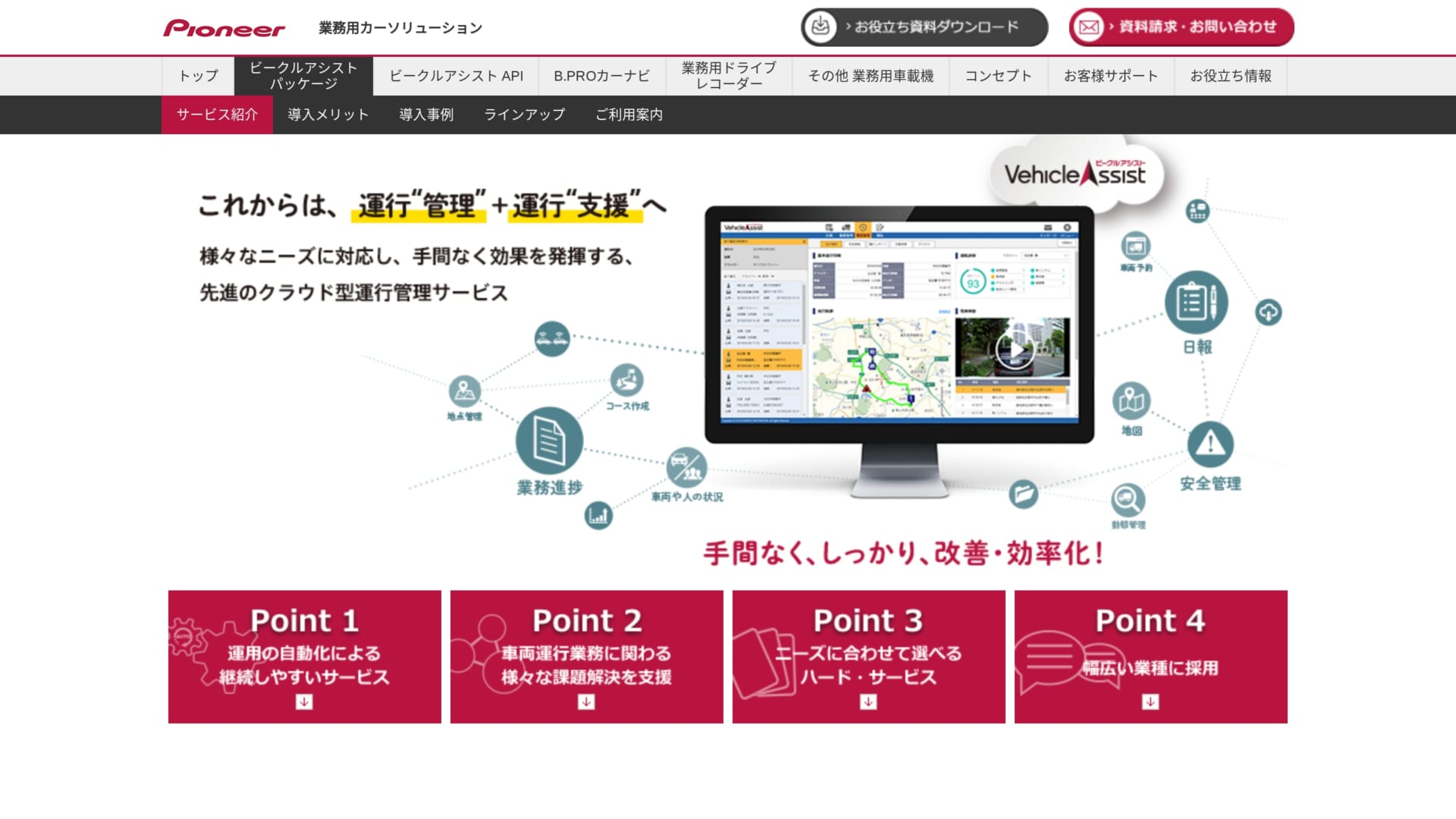あなたは、「AIと会話ができる時代」が到来していることを知っていますか?
現在、LINEでコミュニケーションができる「りんな」やドラマとタイアップした「AI 菜奈ちゃん」「AI カホコ」など、バリエーション豊富なチャットボットや音声での会話が可能になっています。
会話できるAIは、「チャットボット」「ロボット接客」「観光地案内」など、さまざまな分野に応用できることが特徴です。
この記事では、そんな会話ができるAIの具体例から、仕組み、今後の展望まで解説していきます。
AIと会話できる仕組み
AIが人間と会話する仕組みを作るには、大きく分けて3つのプロセスを踏む必要があります。
・人間が書いた言葉を正しく認識する(音声の場合)
・人間の言葉の意図を解釈する
・言葉に対して適切な言葉を返す
ここでカギになるのが自然言語処理という技術です。自然言語とは、私たちが一般的に話している言語で、これをコンピューターが解読可能な形に変えることを自然言語処理といいます。
自然言語処理の精度が、大きく向上することで、より自然な会話が可能になりました。
▼自然言語処理について詳しくはこちら
テキストの会話ならチャットボット
AIと会話する方法で最もメジャーな技術は、「チャットボット」です。その実態を解説していきます。
チャットボットとは
チャットボットとは、自動化されたタスクに従って会話をするサービスを指します。一口にチャットボットと言ってもその在り様は実に多様です。
ここでは簡単に解説しますが、さらに詳しくチャットボットについて知りたい方は以下の記事をどうぞ。
▼チャットボットについて詳しくはこちら
▼チャットボットのサービスマップについて詳しくはこちら

チャットボットの種類はAINOWがカオスマップにまとめただけでも88社(サービス)があります。
チャットボットは大別して4つに分類できます。
- ログ型
- 記録された会話ログを学習して、入力されれた文脈を解釈して返答
- 選択肢型
- シナリオに沿ってユーザーが選択式で回答
- 辞書型
- 複数の単語を登録し、対する返答を返す
- 選択肢型&辞書型
- 選択肢型・辞書型の両方を使えるチャットボット
それぞれにメリット・デメリットがあります。自由な会話という意味ではログ型が適しているでしょう。
なお、チャットボットのサービスは今なお続々と登場しています。今後の発展にも期待大です。
チャットボットの事例
ここからは会話自体を楽しむための雑談型、やり取りによって目的を達成するための非雑談型に分け,チャットボットの事例を紹介していきます。
雑談型
りんな
りんなは、日本マイクロソフトが開発しているAIです。2015年8月にLINEに登場以来、サービスを拡大しています。検索エンジンおよび、蓄積されたビックデータに基づき、高い精度での多様なコミュニケ―ションが可能です。
現在は歌に力を入れていて、公式HPには下記のように「りんな」のビジョンがまとめられています。
りんなは「AIと人だけではなく、人と人とのコミュニケーションをつなぐ存在」を目指している、いま「日本で最も共感力のあるAI」です。
りんなを口説いてみた結果▼
AI 菜奈ちゃん

AI菜奈ちゃんとは、ドラマ「あなたの番です-反撃編-」とタイアップしたチャットボットです。登場人物菜奈ちゃんのAIが作中に登場するのを再現したものです。
LINEで友達追加すると会話が可能です。特にドラマを見ていた人は楽しめるコンテンツになっています。
かたらい

引用:https://www.katar.ai/
NTTが開発したチャットボットであるかたらいは、さまざまな形態に対応できるサービスです。
顧客それぞれのスタイルに合ったキャラクターを一から構築することが可能であるのに加え、学習しながら向上していく質の高い会話や導入時の低価格などが強みになっています。
雑談が可能となっていますが、導入の仕方によっては非雑談型のチャットボットとして活用が可能です。
非雑談型
AIさくらさん

引用:https://tifana.ai/
AIさくらさんは、企業向けに開発されたチャットボットサービスです。
業務の効率化やDX化を目的として導入する企業が多く、社内外の問題を解決するヘルプデスクとしての働きを期待されます。
HP上での問い合わせの自動対応から商業施設や駅での非接触での検温や受付の自動化まで、幅広くおこなうことができます。
音声での会話も徐々に実現
これまで紹介したAIは、文字によって会話するものでした。しかし、近年では音声によるコミュニケーションの可能なAIが実用レベルで登場しています。
音声で会話するAIは、どんな場面で活用されているのでしょうか。
まず思いつくのがコールセンターです。ある程度やりとりをパターン化できれば、AIに代替できます。24時間、人に負担をかけずに稼働できるのは魅力的です。
音声で会話できるAIの事例
雑談型
Romi
mixiから2021年4月21日に発売される最新の会話AI「Romi(ロミィ)」は、定型を持たない会話を行うことが魅力のひとつです。
過去の会話データを記録し、自然な会話の流れが作れることに加え、「オーナーの好みを学習する」「季節や時間帯などその時のさまざまな要素を加味する」などの技術を使うことで、最適な返答を行います。
購入後も随時、語彙力の強化や会話精度のアップデートを行います。
非雑談型
Duplex
Duplexは、Googleが開発した電話予約代行サービスです。
美容院やレストランなどでの電話での予約を自動音声で可能となっており、Google アイスタントを介してデバイス上でバックグラウンドで行われます。
commbo
commboは電話の業務をそのままAIに代替するサービスです。滑らかで自然な発音を実現していて、人件費の削減が期待できます。
自社システムと高度に連携したい法人のために、クラウドAPIも提供しています。
LINE AiCall

引用:https://clova.line.me/
LINEが法人向けに提供しているサービスとして、LINE BRAINがあります。チャットボット、音声認識、音声合成、OCR、画像認識など、多様なサービスを法人に向けて提供しています。
そのサービスの一つに「AiCall」があります。電話での対応に特化したサービスとなっており、音声認識によってスムーズな予約の受付が可能になっています。レストランなどでの人員不足解消、仕事の簡略化に期待がかかります。
2020年11月からサービス名称を「DUET」から「LINE AiCall」の定め、大幅なコスト削減に期待が寄せられています。
▼LINE BRAINについて詳しくはこちら
AIと会話できる仕組み
AIとの会話はどのようなプロセスで可能になるでしょうか。大きく3つになります。
- 人間が書いた言葉を正しく認識する(音声の場合)
- 人間の言葉の意図を解釈する
- 言葉に対して適切な言葉を返す
ここでカギになるのが自然言語処理という技術です。自然言語とは、私たちが一般的に話している言語で、これをコンピューターが解読可能な形に変えることを自然言語処理といいます。
自然言語処理の精度が、大きく向上することで、より自然な会話が可能になりました。
詳しくはコチラの記事をご覧ください。
今後のAI×会話の展望
今後AIとの会話は、増々社会のなかに浸透していくと考えられます。今後私たちの言葉のやり取りを学習することで、更に活用の範囲の拡大が予想されます。特に電話での対応はAIに代替されそうです。
AIによる会話のサービスは以下のようなメリットが考えられます
- 人件費を削減できる
- 24時間稼働できる
- 会話の「質」が均一
今後ともAIを適材適所で活用していき、人間が得意な、感情的な面を含めたコミュニケーションや想像的な仕事に時間を割くような役割分担も進めていくと良いでしょう。
2020年にはLINEがNAVERとの共同で、世界初の日本語で学習したGPT-3を開発することを発表しました。
OpenAIが開発した英語の超巨大言語モデルである「GPT-3」のように、高性能のスーパーコンピュータの活用、インフラの整備によって今後の日本語AIの水準を大きく底上げすることが期待されます。
2020年の東京オリンピックを含めて、日本への旅行客の増加が予測されます。外国人との会話もAIの活躍の余地があるでしょう。
おわりに
AIとの会話は、日に日に自然になっています。現在でも、定型的なやり取りをチャットボットで行うサービスも増えていて、より自由度の高い会話を機械と行う精度も増しています。
寂しい夜のおともから、仕事のパートナーまで、AIと心を通わせるためにも「会話」は必要不可欠です。今後の発展に注目していきましょう。